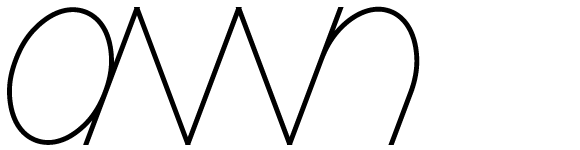
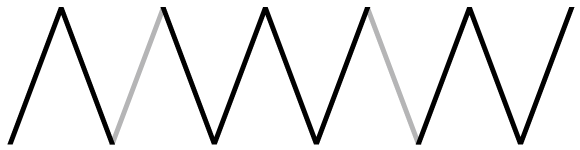
東京という都市を俯瞰してみると、この都市の中心は天皇という一家族が専用使用する広大な森林、その周囲に古くからの良好な都市組織をもつエリア(現在の用途はオフィス、商業、高級な住宅地など)が都市の中心部を構成し、その外に木造密集市街地(用途は完全な住居専用)がリング状に取り巻いている。おそらくここまでが戦前の東京の圏域であろう。このリングより外のエリアは戦後の高度成長期にスプロールした住宅地で、カーペットのように均質に広がっており、最後は混在農地となって都市域が消滅する。
東京は明治以降、3回の大きな面的破壊を受けている。1923年の関東大震災、1945年の第二次世界大戦の東京大空襲、そして1960年あたりから始まる高度経済成長期の開発による緩やかな破壊である。木造密集市街地が形成されるのはこの3回の面的破壊が関係している。関東大震災以前の東京は古くから組成されていた市域の外側を環状に生産緑地帯が囲んでいた。関東大震災で焼失したのはこの古い市域の3,834haにあたる部分で、このほとんどは帝都復興事業が施行され区画整理が行われた。しかし市域周辺部にあった生産緑地帯は基盤整備が行われないまま乱開発されたようである。東京大空襲ではこの区域も含めた市域の全域にわたり16,230haが焼失しているが、戦災復興事業はその7.6%足らずの1,233haしか施行されていない。関東大震災後の帝都復興事業が施行された中心部を除く大部分が、基盤整備が行われないまま広域に乱開発された。この東京大空襲直後、市域周辺部に円環状に生成された木造密集市街地を木密リングと呼ぶ。
1960年頃から始まる高度経済成長期には都心部へのアクセスが良いため、この地域には民間木造賃貸住宅や住宅開発が進行する。宅地の細分化、建築物の高密度化、農地の宅地化などが進行し、現在の木造密集市街地が形成された。東京都ではこのうち不燃領域率60%未満の地域を木造住宅密集地域に指定しており、その面積は約16,000haという壮大な広がりを持つ。さらにこの地域のなかで特に老朽化した木造建築物が集積し災害時に大きな災害が想定される地区を木造密集市街地整備地域に指定しており、その広さも約7,000haという壮大な面積である。
これまで東京という都市は関東大震災の復興事業が施行された中心部(ほぼ山手線の内側)によって語られてきた。巨大再開発はここで行われ、都市を表象するシンボリックな建築はこの中心部におかれたものである。一方、外周部にあたる木造住宅が密集する市街地は東京の都市構想からは除外された匿名的なエリアである。ここは、葉脈のように細街路が入り組み、公園などの公的な空地が少ない密集した住宅地で、土地は細かく細分化されて所有されており大型の開発は困難である。ここでは狭小な宅地に、老朽化した木造住宅が隙間なく建て詰まり、道路は4m以下の狭隘である場合が多く、敷地のなかには未接道敷地も多い。地震があれば多くの建物が倒壊し、さらに火災が伴った場合は延焼を止めることはできず大災害となることが予測されている。そのため早急に整備をしなければならない地区とされている。それでもこの状態が維持されているのは制度的に変化しづらい要因もあるが、定住している住人がこの生活環境を評価しその現状を選択した結果でもある。この地域は東京の中心に近く都市施設の利用など生活の利便性が高いので、高齢化が進みながらも世代交代が行なわれ安定したコミュニティが存在している。この木造密集市街地は緊急に整備を要する大きな都市問題であると同時に、この居住環境は居住都市としての可能性を示しているともいえる。
我が国の人口の増加が止まり、東京都の区部では世帯数人数が2,0を切るという社会状況の変換点をむかえている。そこでは、これまでの都市拡張を前提とするものとは異なる都市の構想が求められている。「都市化社会」が終焉し「都市型社会」に移行したなかで、生活を中心とした都市構想の提案は、都市中心部ではなく防災上変化せざるを得ないこの木密リングの未来構想のなかに求められているものである。
この東京の木密リングのような匿名的都市組織に対する論考として、学生時代に読んだ「あなたには〈普通〉はデザインできない」というN.J.ハブラーケンの論考は印象的であった。おそらく1971年に出版されたこの文章の背景は、それ以前にSAR(Foundation for Architectural Research)で展開していた作業を通してその時代を俯瞰したものである。ヨーロッパの都市は都市組織と呼ぶ匿名的な連続構築物で埋め尽くされており、フリースタンディングの建物は教会など公共の特別な施設しかない。だからヨーロッパ社会ではfigure ground map(図地地図)というアイデアが誰でも簡単に了解される。そのなかで、建築家は歴史的(モダニズム以前の近代社会)には「図」となるシンボリックな特別な建物にしか関与していなかったとし、都市の中で「地」となる匿名的な都市組織には建築家は関心を持たなかったとする。20世紀初頭に王権や宗教権力の支配する社会から市民社会へ移行したために、建築家のクライアントが入れ変わり、対象とする建築も市民が利用する工場や住居となる。しかし、現代の建築家はそのような普通の建物までも特別なものにしてしまう。だから「あなたには〈普通〉はデザインできない」ということになるのだ。ここでは建築家の職能概念は社会制度に対応して変化するということが言及されている。
有名な挿絵がある。コルビュジエのドミノシステムのダイアグラムに×印を付け、その横に日本の伝統的な住居の板図を並べている。板図というのは大工が現場で使っていた板に描いた平面図である。日本の伝統的住居は「間」というモジュールで空間が構成されているので、タタミのモジュールを使って素人でも間取りを作ることができる。それがそのまま板図になり木割のシステムによって木造軸組の構造体が自動的に決まるのだ。日本ではユーザーの描く間取り平面だけで立体的な建築が組み立てられるという社会システムが存在する。近代以前の日本では匿名的な都市組織を統御する社会システムが存在していた。だから災害で家を失っても容易に風景が再現されるシステムが社会に内在していたといえる。ここで、ハブラーケンはコルビュジエを否定しようとしているわけではない。ドミノシステムという実体としての構造躯体が普遍的な回答ではなく、板図の背後にあるこのような社会システムがそれをつくるということを示そうとしているのだ。ハブラーケンは「住まいとは住むという行為以外の何物でもない」として、住まいというレベルは当事者以外にはデザインできないとする。ここでは建築という領域そのものの拡張が言及されている。この小論は住宅という単体の建築を超えて都市組成に意識を向かわせてくれるものであった。SARでは個人が意思決定を行う住居という都市の最小単位から地域社会、さらには都市にまで参加する階層的な社会構造が研究されていた。
ハブラーケンのアイデアは1960年代半ばから提出されていたモダニズム批判を原理的に批評し、静かなプラグマティシズムの立場から社会を先に進めようとするものであった。当時の情緒的でファナティックなモダニズム批判とは異なり、C.アレグザンダーの「A City is not a tree」(1965年)とタイトルされた論文に描かれたダイアグラムを具体的に再現する手法がイメージされていたのかも知れない。その後、1991年にソビエト連邦が崩壊し、世界は資本主義に対抗するイデオロギーは不在となり、資本の暴走が始まる。建築の主要なクライアントは巨大資本となり、その存在を表示するアイコン建築が大量に生産されるようになる。
2008年の市場資本主義のクラッシュまでの期間、建築の世界にイデオロギーは存在していなかったのかもしれない。不思議なことに1978年に書かれたレム・コールハースの「Delirious New York」以降、建築の世界には都市にかかわる重要な論文は提出されていない。建築に思想は必要のない時代であったのかもしれない。
そんな時代状況を感じながら「生成変化する都市(Tokyo Metabolizing)」という2010年のヴェネチアビエンナーレの展示コンセプトを検討した。都市の航空写真を眺めていると都市ごとに全く異なるパターンを持っていることに気づく。パリ、ニューヨーク、東京は同じ人間が地球上に生息するための物理的環境のはずであるがその姿は全く異なる。都市は物理的コンテクストと文化的コンテクストが複合して都市組織が決められているのだが、さらにその上位にある社会制度を支配した権力の思想が反映する。歴史上存在した、あらゆる都市は何らかの偏在する大きな権力によって形作られてきたといえる。
19世紀半ばのパリでは、ナポレオン三世による帝政の強大な権力の下、1850年代から20年ほどの短い期間に、オースマンというひとりの行政官の意思によってコントロールされた壮大な都市空間が形作られた。そして、20世紀初頭のニューヨークではセンターコアのオフィスビルが入る平面を基準にゲーム盤のようなグリッドシステムの街区が用意され、そこに最大効率を求めるボリューム操作が行われ、巨大資本を表象するスカイスクレーパーが建設される。1920年代の10年ほどで一気に摩天楼が建ち並ぶ都市風景がつくられた。これは人が住むための都市ではなく資本主義のシステムがつくる都市である。
世界の巨大都市のひとつである東京は、小さな土地に細分され約120万という所有者に分割されている(この場合の東京は東京都の特別区を指す)。それぞれの土地には建築規制がかけられているが、そのルールさえ守れば土地の所有者には自由に建物をつくる権利が与えられている。その小さく細分して所有されている土地のほとんどは生活を営む住宅なので、ライフサイクルに対応して建物は増改築が行われ変化する。だから、東京の建物の平均寿命は26年しかない。ヨーロッパの都市は人間の生命スパンを超えて存在するため、都市空間は実体として認識され、人には変化は感じられないのであるが、東京では数十年もすると風景を構成する建物はほとんどすべて変化してしまう。そこには空間を支配するイデオロギーは不在である。
2008年の資本主義経済のクラッシュによってもたらされた社会システムや都市概念の変更要請は、2011年の東日本大震災を経験したことで、より切実なものとなっている。私たちは文明の切断面にいるのかもしれない。経済活動を中心に構想された20世紀型の都市モデルから次のモデルに移行することを検討するステージが見えている。それは東日本大震災で街や集落が消し去られた現場を見たという事実と、福島で起きた原子力発電所の被害によって都市のエネルギーインフラに関して深刻な問題を突きつけられているからだ。生活の手掛かりとなる街のありかたを再考し、エネルギー消費を抑えた持続可能な都市への移行が切実に検討されるのである。
20世紀型都市モデルは19世紀末のシカゴで開発された。それは、都市の中心部にオフィスビルが立ち並ぶ業務中心地区、郊外には都市労働者を収容する専用住宅地を設け、その両者をつなぐ交通インフラを放射状に整備するという、経済活動に対応したものである。この都市モデルによって都市の中心と郊外を毎日往復運動するという現代生活が作り出された。都市は用途によってゾーニングされ、それをつなげるために交通やエネルギーのインフラは巨大化する。第二次世界大戦でほとんどの都市を焼失した日本は、経済活動に対応するこの都市モデルにつくり変えられ、高度経済成長期を支えた。一方、都市の中心部の旧市街に連続壁体の都市組織をもつヨーロパの諸都市はこの都市モデルは持ち込まれない。20世紀型都市モデルに改造するためにパリの中心部を破壊して超高層ビル群を林立させるというコルビュジエのヴォアザン計画は採用されなかった。ヨーロッパの人々は都市の中心部に安定した都市組織である、旧市街を保持したままの都市構造を選択する。それは、経済活動に効率的に対応できないため、旧市街の内部が荒廃する深刻なインナーシティ問題を抱えるのだが、小さな公共的手だてやリノベーション、遅い交通網の整備やトランジットモール化によって旧市街は人間の生活を中心とした持続可能なコンパクトシティとして再生している。
東京はその周囲に土地が細かく区分所有され整備が進まない木密リングを抱えており、インナーシティ問題と同様の様相を示している。この木密リングをヨーロッパの諸都市で試みられたように居住環境として再生できれば、この都市は20世紀型産業都市と並列して、人々の多様な生活の場に対応する居住都市が存在する二重構造の都市(デュアル・シティ)として構想できる。それは都市の中心部と周辺部がまるで異なる二つの都市のように自律して共存しているというイメージである。
2011年の秋に行われたUIA東京大会で「Tokyo2050」という東京の2050年の未来ビジョンを提示する展覧会に木密リングの都市組織を未来型の居住都市に生成変化させるプロジェクトを提出した。前年にヴェネチアビエンナーレで自動生成する東京の都市イメージの展示をしたこともあって、巨大なインフラではなくローカルなインフラや小さな空間的手立てによって「都市を誘導する」という計画手法を考えた。2050年という設定は、人間の生命スパンを越えないが、社会状況の大きな変化は想定できるという時間である。直近の都市問題を扱うわけではないので、都市を理念的に捉える時間距離がある。国全体の人口が縮減するなかで、持続可能な社会をどのように設計するのかその回答が求められる。これまでの都市計画ではモビリティが重要な要件であったが、そのむやみな拡大は抑制し、選択肢の多い交通手段が用意される必要がある。都市内は機能の混在が進み、働くことと住まうことが自由に行き来できるライフスタイルがあたりまえとなり、その機能混在を緩衝するクッションのようなボイドが重要な都市要素となる。それは小規模な公園やギャラリーなどの自由に誰でもが入って使える空間であり、カフェやレストラン、マーケットなどの商業施設というこれも誰でもが入れる施設がネットワークされ近隣を取り巻く泡のように設けられる。そしてクリニックやスポーツジムなどの生活をサポートする施設が分散して身近に存在する。歩いていける生活の圏域には快適な外部空間が様々な形で遍在し、そこに人々は滞留する。この街では人とので出会いが多くなる。ここでは、外部空間や所有のあいまいな誰でも使える空間が多孔質なスポンジのように編み込まれ、それがボイドのネットワークを形成する。所有のあいまいな空間がコミュニティを醸成するのだ。この居住都市はコミュニティが連鎖する「超混在系多孔質都市」というものである。
それは東京都の木造密集地域整備事業対象地区を、いくつかの操作(モビリティ、エネルギーなど)を行いながら都市の環境単位としての可能性を検証するものである。たとえば、車の侵入を排除することによって道路をコモン(共有地)の領域に参入し、土地を所有するのではなく使用するという概念を形成する。共同建替えによってグレインを変更させ、外部空間に対する新しい設計理念を導入する。さらに、変換のインセンティブを与えるマネージメントにも言及しなければならない。そこでは、心地よい戸外生活が営まれる豊かな外部空間を持つ新しい生活ユニットが構想できるであろう。そして、当然のことながら、この都市ではエネルギーの使用レベルを圧倒的に下げるインフラを構想しなければならない。そんな内容を入れた提案である。
木造密集市街地に再開発整備地区を設けても整備が進まないのは、土地が小さく区分所有され権利関係が輻輳しているためである。ここでは強制執行をともなう再開発事業や道路整備ではなく自律的な変化を誘導する方法を提案する。「路地核」と名付けたエレベータと階段の垂直導線を、道路のように公共が用意するインフラとした。人間が自力で上り下りできる4階建を想定している。この「路地核」は地下に自助消火活動が行える防火水槽とポンプを備える。Tokyo2050の展示では、「路地核」の各階の踊り場にコミュニティキッチンやシャアハウスのための設備、屋上菜園などを提案した。空間構造としては「祐天寺の連結住棟」のコア棟のような役割で、この「路地核」に接続してルームを設けることができる。木造密集市街地のなかでは、未接道敷地といわれる法的に建築物を建てられない不適格敷地が多数存在し、その土地が塩漬けとされこの地域の開発が進行しない原因になっている。このような不良宅地を含む複数の敷地の共同建替えの計画である。共同建替えの敷地の中に行政の支援で「路地核」をインフラとして設け、周囲の地主に共同建替えを誘導するものである。共同建替えではあるが地主は土地を所有したまま自宅と借家を安価に造ることができる。エレベータの保守点検を公共が行うことにしているので周囲の地主は階数を積むことができる。
土地が細かく区分所有されているのはそのままとし、建蔽を下げながら(空地を増やしながら)容積を積むことができる。上階にオーナーが住んで地上階を店舗または自らのオフィスにしたり、高齢のオーナーが地上階に住んで上階をシェアルームにするなど、共同建替えの動機づけとなる余剰の床が生まれ、その場所の高齢化の進むコミュニティを保持したまま、新しい若いコミュニティの参加を求めていくというものである。細街路は共有地(コモンガーデン)のように扱い、各敷地に生まれる空地をコモンに供出することを誘導する。連続する外部空間は防火樹を植えて延焼を防いだり、避難経路になるなど防災上有効な空間になる。そして相隣関係を調整する空気のクッションとして働き、この木漏れ日や隙間風のある快適な生活環境を作り出すコモンガーデンがコミュニティを支援するというものであった。
自動生成する私たちの社会では、現在の社会活動にヒットする建築類型(タイポロジー)が発見されれば、一気に都市の風景が変わる可能性を持っている。新しい思想をもった建築の登場が新しい社会を出現させる。それが、社会システムが創る都市であり、建築の主題はその新しい都市組成となる単位の開発であると考えている。都市は人の住む場所である。戸建て住宅の海で埋め尽くされていたこの都市はゆっくりと変化を始めている。それは、巨視的に見れば多数の個別の意思が参加しながら全体としての最適解を得る見えないシステムが存在しているようにも思える。それは、ハブラーケンが指摘していた社会システムが自動生成するように創る都市であるのかもしれない。
昨年は森美術館で「メタボリズム展」が開催され、レム・コールハースによる「Japan Project」というメタボリズムの実像を探る厚い本が世界で出版された。1960年にメタボリズムという概念が日本からが発信されてから半世紀が経つ。メタボリズムのアイデアは第二次世界大戦で焦土とされた廃墟の風景(タブララサ)からスタートする。メタボリズムは都市に対する思想であり、建築は壮大な都市を形作る部品であるから都市のイメージを持つことが要請されていた。丹下研究室から発表された「東京計画1960」の美しい模型はメガロマニアックなオブジェのように見えるが、それは社会からの要請に応える誠実な回答である。急速な産業社会の拡大に対応して都市への人口圧力が高まり、東京は都市構造の変革を求められる。一度、廃墟になった都市であるが、その既存の都市にはほとんど手を付けず所有者不在の海上に都市軸と呼ぶハイウエイを延伸し、そこに住居とオフィスを機能的に配置する1000万人の都市を開発するというものであった。
現代では、このメタボリズムで展開された実体としての建築的アイデアはリアリティを失っているのだが、東京という都市状況は依然として生成変化を続けている。東京の中央部は他の都市と同様、様々な権力(資本や国家の)アイコンとしての建築が立ち並び世界のどこにでも見られる都市様相を示している。しかし、その周辺にある住宅地は匿名的な小さな粒(グレイン)で埋め尽くされており、その小さな粒(グレイン)が絶え間なく変化している。木密リング全域の16,000haという壮大な木造密集市街地は、「東京計画1960」に匹敵する計画規模を持つプロジェクトサイトである。半世紀前に提出された東京計画は、海上というタブララサの上に描く新都市構想であった。そこでは社会にある問題群にたいする回答をひとつの実体としてのカタチで示されている。しかし、木密リングの問題群にたいする回答は既存のコンテクストに答える多層のレイヤーをもつ回答群となる。それは建築的なカタチだけではなく時間概念をもつ制度的なシステムにかかわるもので、空地や公共施設で構成されるボイドネットワークであったり、自律的な生成変化を誘導する社会制度で示される。この生成変化の現場はタイポロジーの多様な空間展開となるであろう。これは計画の主体が一つではなく多様に多数存在するという計画である。
この木密リングに構想するものはコミュニティの連鎖である。家族のための戸建て住宅ではなく、もう少し大きな中間集団の生活そのもの、働く場所や憩う場所も含めた多様な活動に対応する都市組織の単位となる。そしてこの居住都市を形づくる主体は、政治的権力や資本権力ではない匿名的社会集団(コモンズ)となる。資本のグローバリズムの中でこの国の製造業や輸出産業は不安定な経済環境のなかに置かれている。そのなかでエネルギーや環境に対する新しい思想が登場しており、それに対応する新しい技術が開発されている。このような状況がここに記述してきたような新しい社会生活に対応する新しい都市組織の開発を要請しているのだ。この国は匿名的な社会集団が主体となる都市づくりに舵を切ることができるのか。文明を創る壮大な経済活動のフロントがそこにある。
新建築2012年8月号 建築論壇に掲載