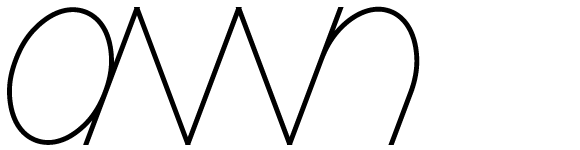
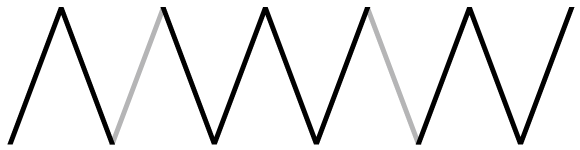
雑誌の集合住宅特集というのが組まれていても、そこで紹介されている集合住宅のほとんどは東京都市圏のものだ。東京という都市が大きく再編されていく中で、人々が集まって住むという方法も変化している。
20世紀が終わろうとしていた1990年代、バブル崩壊の経済不況のなかでも元気の良い経済活動として「デザイナーズマンション」という商品が注目されていた。 それまでは都内のマンション業者はマンション用地と呼ぶマンションを開発しやすい、整形で道路付きがよく、まとまった土地を仕入れることが主要な仕事であった。事業用マンションという建築物は想定されたモデルが明らかに存在していて、想定されたモデル以外の解では法的に何らかの抵触があったり、または経済効率が落ちる。だからマンション事業というのは事業立地のあるエリアに想定モデルが納まるマンション用地を取得することが主要な仕事であり、建物の設計には大きな意味はなかった。マンション業者は立地によってワンルームであったりファミリータイプなどの事業企画をたて、マンション設計に手慣れた事務所やゼネコンに設計を依頼する。そのように設計されたものに商品のグレードを決めることがマンション業者の主要な商品開発の作業であった。このような大手ディベロッパーの商品は、戦後日本の建築計画学が開発し日本住宅公団や各地の住宅供給公社によって展開された理念モデルnLDKがベースとなっている。その同じ間口のnLDKユニットを長い廊下を介して並べ、階段やエレベーターを少なくして事業効率を上げるという形式である。建築基準法や消防法に対応し、東京都の安全条例などの制度がこの事業用マンションの形式を前提として後追いで作られたことで、このモデルはより強固に守られることになった。日本独特の集合住宅形式だと思う。 「デザイナーズマンション」はバブル崩壊後の経済不況の中で生まれた新しい経済モデルだったのかもしれない。資本原理とは無限の再生産というオートマティズムが内在するため、その都度設計与件が変わる一回性の建築は効率が悪いので通常は商品とはならない。標準設計の事業用マンションが建つマンション用地はそのオートマティズムに対応しているのだが、これは敷地条件の悪い土地を個別の設計によって事業化しようというものである。事業用のマンション用地での計画では建物の設計技術にはたいした意味はなかったのであるが、不良な土地では建物の設計技術によってその商品価値は大きく変わる。だから「デザイナーズマンション」とは設計技術を商品化する経済モデルだったのだ。東京の都市圏では、20世紀から21世紀に移行する時期に確実に安定した都市型社会に移行している。世界の経済は地域経済から世界ブロックでの競争と競合が進行した。その社会の変化に対応して都市の再構成が東京の様々な場面で進行している。都心部では新しい資本システムに対応する巨大再開発がおこなわれ、臨海地区では産業構造の変革にともなう開発がおこなわれている。そこでは超高層分譲マンションという新たなオートマティズムが始まっているのだが、同様に都市部の大多数を占める戸建て住宅の密集地の再編成も都市の構造的要求なのだ。密集市街地の小規模集合住宅は東京という都市の再編のなかで構造的に要求された新しい経済モデルなのだ。
1980年代、大手ディベロッパーが創り出した「億ション」という商品はマンション用地に建てられた標準設計の事業用マンションに、様々な付着物(大理石の床、シャンデリア、金めっきのドアノブ、システムキッチンやユニットバスなどの住設備のグレードなど)を付けて商品価値を生み出していた。住戸プランはどれも大差はなく、そこで想定されている生活様態もステレオタイプである。たとえば南向きのベランダにリビングが設けられ、そこにはシャンデリアがぶら下がって革張りの応接セットが置かれる。ダイニングテーブルの上にはペンダントライト、キッチンは人工大理石天板のシステムキッチンが置かれる。分譲マンションはモデルルームを重要な販売ツールとしているのでモデルルームの家具レイアウトには専門のコーディネイターが付き、幸せな家族生活を精一杯演出する。その生活はファンタジーに満ちたステレオタイプだ。モデルルームを訪れる人は住宅というハードウエアではなく、そこでイメージされる幸せな家族生活を購入していたのかもしれない。その時代にはそのような商品を購入するマーケットがコアとして存在していると考えられていた。 1990年に入るとバブル崩壊によって不動産価格が暴落した。高額の分譲マンションが市場から姿を消し、賃貸マンションが集合住宅の主役となっていった。 密集市街地の小規模集合住宅は、事業用マンションとしては成立しない敷地がほとんどである。もともとはその土地を持つオーナーが住んでいた小さな宅地で、道路付きの悪い土地や旗竿敷地、法的な制限を厳しく受ける土地など、それまでは事業用としてのマンションは計画されなかった敷地である。そんな不自由な条件の敷地のなかで集合住宅を成立させる多様な設計技術が試みられている。それは標準設計に付着物を付けて商品価値をつくるのとは異なり限界点での設計技術によって事業性が創られる。その設計はまるで数学の問題を解くように論理的に解が求められる。恣意的な操作によってコストを上昇させないということを事業指向クライアントに対するエクスキューズにするため、ある種の社会的な判断や合理的な方法論が織り込まれている。それはマンションという不動産屋の営業が主導する商品技術ではなく建築家が主導する環境技術のようなものが事業を成立させる要件となっているようである。 それらの技術を以下に列挙する。
コストを上昇させないためになるべく単純な構造体とする。敷地形状が不整形であったり斜線制限を受けて変形する場合が多いので形態を単純化させようという意志が働いている。そして、構造体そのものを意匠表現とすることが多いので構造の躯体寸法や構造システムが厳格に決められている。低層のものが多いため壁床ラーメンやフラットスラブを用いて住戸内に梁型を出さないような構造形式がとられることが多い。余計な仕上げをしないとか空間を合理的に使用しようとすることで躯体そのままを仕上げとするものが多い。
敷地形状が整形ではなかったり小規模であるため、南面する住戸にこだわると計画が成立しない場合が多い。南面しない住戸であっても商品として成立するような環境技術の工夫がされる。法的に要求される採光を北側の窓とし、直射光が入らなくても大きな開口部を設けて室内の明るさを確保するとか、クロスメゾネットなどのプランニングで方位の問題を解決するものもある。賃貸の小規模集合住宅では、基本的には日中ほとんど在宅しない住人を対象としていること、ベッドでの生活となっているので布団を干すことがないことなど、南面するという方位には無関係に計画ができるようになっている。
都市型社会では家族形態は大きく変化している。家族という形態を取らない少人数の住まい手では、住戸内でのプライバシーは不要になるので住戸内を細分化する必要はない。さらにSOHOのようにそこをオフィスやアトリエとしても使用することも想定するとワンルームであるほうが都合がよい。または生活様態を計画側が規定するのではなく、住まい手が空間の使い方を決めるとするならば間仕切りはない方が空間の自由度が高い。ここではnLDKという空間を機能によって区分することには意味が無くなっている。平面的に間仕切壁がないワンルームであるだけでなく、メゾネット、トリプレックスなどの多層階で仕切りのない立体的なワンルームの住戸も作られる。これも敷地条件が悪いために長屋形式の集合住宅となる場合や、空間効率を上げながら住戸内の環境条件もあげようとする設計技術である。
分譲の事業用マンションでは豪華な設備施設が商品価値を作っていたのであるが、賃貸の小規模集合住宅では空間性能が重要視されるので、キッチンやバスに大きなスペースは取らない。毎日料理をするような生活には対応していないのだ。逆に必要最小限の設備が合理的に設けられていることのほうが重要である。オフィスやアトリエとして使用を考える場合はバスタブはなくてシャワーブースだけであったり、キッチンではなくキッチネット(簡易キッチン)のほうが空間効率がよいのであるが、このオフィスのような空間を住居とするのである。
密集する住宅地のなかで、しかも変形の敷地に集合住宅を計画すると通常の標準設計のマンションのように南面に同じ開口部をもつ形式とはならない。方位には無関係に開口部を設けることになる。その開口の位置は周辺の風景や隣家の窓、そしてわずかな隙間をねらって設けることになる。周辺の微細地形に反応した開口部なのだ。それぞれの住戸に細やかな配慮をした環境技術としての開口部が要求される。
東京都内で計画する事業用マンションでは南面するベランダの前に窓先空地と避難通路を設け、北側は高度斜線などで離隔距離を要求されるため、南側と北側に何となく空地が生まれる。そのような意味づけの希薄な外部空間ではなく、密集市街地のなかで小さな規模の敷地で計画する場合は安全条例で要求される窓先空地や避難通路までも外部空間の環境性能を上げるために配置しようとする。小規模集合住宅では建物の残余となる外部空間も重要な計画要素なのだ。
ここまで記述してきた20世紀末から21世紀初頭にかけて登場した、密集市街地の小規模な賃貸集合住宅は東京の都市構造の再編に連動していた。都市内で大きな面積を占める密集市街地の中で小さな資本による小さな規模の建物の再編なのだが、経済行為としては土地を持つオーナーにとっては安全な資産運用の方法の一般解であるため、都市全体としては都市の様相を一気に変換する運動なのかも知れない。大規模な再開発の大手ディベロッパーの事業用マンションではどれも同じ標準設計の建物に商品として付加価値を付ける商品技術が要求されているのに対して、この小規模集合住宅では多様な個別の敷地に対応する設計技術によって事業を成立させるものである。すなわち空間そのもの性能を確保することが事業性を担保するという環境技術が要求されているのだ。
この数年で集合住宅の様相が少し変わってきているように思う。密集市街地に計画される小規模な集合住宅は、かつて木賃アパートと呼ばれたビルディングタイプの新しいバージョンである。集合形式は小さな住戸ユニットをプライバシーを守りながら高密に集合させるものである。そのため小さなユニットをつなぐ長い廊下が必要となり、また厚いコンクリートでユニット間が切れる壁床ラーメン構造が多用されていた。このような小規模集合住宅はモダニズムの計画原理に基づいている。基本的には個に分解された個人を収容する集合形式であり、住戸のプライバシーを確保することが優先される。分断された個をつなぐものは住戸外に用意されるコモンの空間である。 新しく出現している集合形式は、都市生活の中で個が分解されコミュニティの感覚が希薄になっている事に対して、集合して住まう意味を見出そうとするものである。ユニット間に視線の交錯が生まれるものや、かつての長屋のように路地を通して行き来ができるものなどである。これらは「プライバシーの系」から、集まって住まう「気配の系」へという動きがあるようである。その「気配の系」とはお互いの生活の気配を感じられる緩やかなプライバシーの空間構成をとるものである。鉄扉を閉じれば中で何をしていても分からない近隣ではなく、お互いの気遣いや心配りを必要とする空間である。夜、明かりが灯ることで隣家の帰宅がわかったり、外部の近隣にも生活の滲み出しがあるような空間構造である。そんな緩やかなプライバシーをつくる道具立ては、かつて連獅子、連格子、簾、無双窓そして障子など京都の町屋で普通に用意されていたものである。共同体が存在していた当時の都市では集まって住むと言うことはプライバシーの問題ではなく、気遣いや心配りという作法が大切な要件であった。現代の都市ではプライバシーの系を主要な要件として集合形式を組み立ててきた。その集合形式がさらに共同体の意識を希薄にさせてきたのかもしれない。今、「気配の系」というような集まって住まうことの意味を考え直す空間が提案されている。 そしてそのような空間の提案は開口部に関係する事柄となるため、視線だけではなく光や風もルーズに内部と外部を行き交うような構造となる。高気密高断熱でさらに遮音性能まで要求する「閉じた住戸」ではなく、気候の中間期には開放して住むことのできる「開かれた住戸」という概念に展開するかもしれない。夏は蒸し暑く、冬は乾燥し寒い、梅雨や長雨があり、春秋のさわやかな時期がある、そんな独特の日本の気候環境に対応し同時にそんな四季の変化を楽しむ空間がある。そして、それを隣人とともに楽しめる集合形式を創造することは可能であろうか。
最近ビルディング・フィジックスという言葉をよく聞く。ファサード・エンジニアリングという外部と内部のインターフェース技術はすでに様々に紹介されていて、日本のゼネコンの技術部ではかなりのノウハウストックはあるようである。ただこのファサード・エンジニアリングという概念は西ヨーロッパで進化した環境技術であるため、日本の環境に対応するスマートな技術確立にはまだ開発時間を要するようである。このファサード・エンジニアリングという概念も包含するビルディング・フィジックスという概念があるそうである。それは、人間の居る物的環境すべてに関わる科学的な思考方法である。日本では建築に関わる技術者は構造と設備だけになってしまうのだが、英国に本社のあるオブアラップ・ジャパンだけが建築に関わるエンジニアリング全般のサービスができる組織である。そこでは構造エンジニアが、建築を計画するその都市の卓越風によって建物の微細気候がどのように影響を受けるかということを夢中になって話してくれる。ここでオブアラップの宣伝をするつもりではない。日本の公共建築を発注する時の工事区分で決まる設備、構造という分類ではないエンジニアの職能がある。 建築を科学的アプローチで見ていく技術は建築の姿を大きく変える。そんな予感がする。