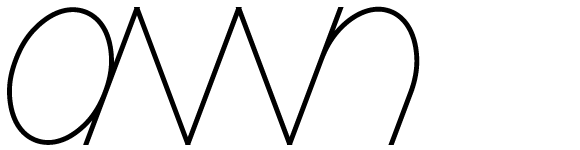
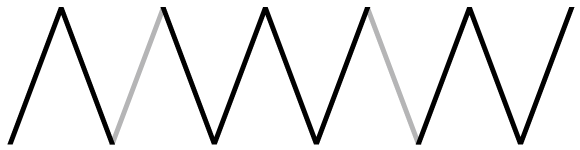
1960年代初頭から70年代初めにかけて、ロンドンから奇妙な不定期刊のテレグラムが発送されていた。“ARCHIGRAM”と名付けられたこの薄手の雑誌はアメリカの大衆漫画のようでもあり、当時、世界中を熱狂させたロンドン発のポップ・ミュージックのLPジャケットのようでもあった。この「アーキグラム」とはそれぞれが大学で教鞭をとるフリーランスの建築家6人がボランタリーに集まったグループで、各自の建築的アイデアを同人誌のように投稿し、それを掲載するアンダーグラウンド誌のような体裁であった。アーキグラムは、その活動時期がビートルズとほぼ重なっていたこともあって、小気味よいポップ・ミュージックのようなメッセージを発信していた。 アーキグラムの提案するものは、テクノロジカルなユートピアと、サイエンス・フィクションの世界が結合したイメージが支配する。たとえば、「ウォーキング・シテイ」と題するプロジェクトは、居住ユニットがプラグ・イン(電球をソケットにねじ込むように取り付ける)された巨大な構築物であり、それ自体が都市である。その巨大な機械の塊のような都市がマンハッタンを背景に群を成して動いているというドローイングである。それは実現不可能な楽天的なアイデアのようにみえる。
アーキグラムの提示するものは、その徹底した馬鹿らしさ故に、建築に付随する権威的象徴をあざ笑っているようにみえてくる。建築とは絶えず権力側や力を持つ側をクライアント(依頼主)とし、その見えない力や制度を具現化する装置として機能していた。20世紀の初頭に像を明確にしてきた建築におけるモダニズム運動は、19世紀までの建築が強い力の側(王権や宗教権力)に立っていたのを人間の側へスタンスを変える革命であった。しかし、そのモダニズム運動も1960年ころにはしだいに新たな力の構図(社会的権威や商業主義)に回収されていくことが明らかとなる。アーキグラムのドローイングによる一連のメッセージは、そんな建築の行く末をもう一度強力に初期設定し直す作業であったように思える。それは建築を漫画のようなポップ・カルチャーのなかに置くことで、大衆のもとに戻す作業である。建築を建てることは莫大な資金を必要とするため、力の側をあざ笑うようなアーキグラムのプロジェクトは実現化する見込みのない作業となる。それ故、この建築家のグループは何一つ実体としての建築は残こすことはなく、ただ紙の上のドローイングだけがメッセージとして残っている。ただ一度だけ、1970年に行われた実施コンペでアーキグラムは1等をとり、彼らのアイデアが実現する可能性があった。この「モンテカルロ」のコンペは巨大なイベントホールの計画で、アーキグラムの回答はその巨大な施設をすべて盛り土のなかに埋めてしまい、外からは小高い公園となった小山にしかみえないというものであった。これはクライアントの都合で実現しないのだが、この提案では建物らしい立面はなく、建築はその姿を消されてしまったようにみえる。このプロジェクトを期にこのアーキグラムの活動はほぼ終了するのだが、徹底した力の側からの撤退が「建築の消去」に終焉したことは(さらに実現しなかったという事実もそれを強化しているのだが)、このアーキグラムのコンセプトをさらに明瞭にしているものであった。
その直後、1971年にポンピドーセンターのコンペの結果が発表されている。建築家レンゾ・ピアノとリチャード・ロジャース、そしてピーター・ライスを中心とするオヴ・アラップの技術者達のチームが1等をとる。この1等案のドローイングをみると、アーキグラムが実現することを放棄して描いていたと思われていたアイデアそのものが描かれているように思える。そこにはテクノロジカルなユートピアとサイエンス・フィクションの世界が描かれているのだ。プラグ・インされた設備機器、脱着可能な部品、露出された工場のようなストラクチャー、同様に露出された設備配管、空中を飛ぶエスカレーターの透明なチューブ、自由にスペースを閉ざしたり連結できる可変のパーテション、可変の床、またアーキグラムのドローイングに多用されたニューマチックのテントが傾斜した前面の広場に描かれている。そして何よりも立面が透明であり内部のアクテイビテイ(人々の活動)はすべて露出される。同時に建築の組立や、空間を支える仕組みもすべて露出されている。
このチームの年代層はアーキグラムとほぼ同じであり、アーキグラムがベースとしたAAスクール(ロンドンにある建築学校)でピアノもロジャースも教鞭をとっていた。だから時代のバックグラウンドや建築の精神はアーキグラムと共有されていたことがわかる。レンゾ・ピアノは、彼の作品集のなかのポンピドー・センターの解説の中で、「美術館という場所は、近年ルネサンス期を迎えた。老いも若きも、住民も観光客も、誰もがピカソを見に、あるいはブランクーシの滑らかな石像の中に詩心を求めて列をなす。しかし、70年代初めにポンピドー・センターが構想された時には、美術館に足を運ぶ者など誰がいただろうか。美術館は、陰気で埃っぽく抹香くさい場所であり、政治の道具であり、要するにエリートのためにつくられたものと考えられていた。」と書いている。このことからもこのポンピドー・センターを構想したときには、アーキグラムが主張していたコンセプトが色濃く反映されていたことがわかる。それは建築が身にまとっていた権威や、ハイ・カルチャーに所属することを示すファサード(建築の正面となる立面)を取り払い、誰にでも開かれた大衆の施設とする意図が読みとれるのだ。その建築的回答が1960年代にアーキグラムが継続して提案していたのと同様に、社会的権威というものに対してそれを無効にするような答えとなっている。アーキグラムのプロジェクトはひとつも実現することはなかったが、このポンピドー・センターでアーキグラムのメンバーではない、ピアノとロジャースによってポップ・カルチャーとしての建築が実体化されることとなる。
アーキグラムは6人の建築家で構成されたチームであったが、アーキグラムの提案するプロジェクトが共通する思想に裏打ちされたものであったために、表出する建築的表現は一貫性をもっていた。そのため実はプロジェクトはそれぞれ建築家の個人的な作業であっても、全体としてみるとアーキグラムは運動体としてしか認識できない。つまり個々の建築家の自己表現としての建築はその運動体の中で匿名となってみえる。同様にこのポンピドー・センターの構想がチームで行われ、さらにその構想を現実の物とする設計も個人ではなくエンジニアを含むチームによって行われているため、この建築では建築家の個人的表現は消去されている。建築のあらゆる部位に関して個人の恣意的な選択は行われず、すべての部位の選択に関するプロセスが説明可能なものとして解決されている。作り手側がチームであるため、部位の決定のプロセスがチーム内で検討可能となるように開示されているのである。ポンピドー・センターは建築家の個人的な表現は匿名的であり、まるで工場プラントの設計のようにわかりやすく構成のシステムが露出されている。この手続きによって、この建築は物的な透明性ばかりでなく、空間を経験する者に空間の成り立ちに対しても透明性を感じさせているようである。
1977年に開館したポンピドー・センターは、美術、音楽、インダストリアルデザイン、文学のための巨大な文化センターである。その敷地の半分以上が大衆に公開された広場となっており、そこではこの施設には収容されないパントマイム、曲芸、ストリートミュージックなどのストリートカルチャーが展開されている。この広場に面するファサードには透明なチューブのエスカレーターが設けられ、透明なガラスごしに内部の活動が明示されている。固い壁をもたないこの建物はこの広場で生起するストリートカルチャーを内部に引き込み建物全体が街路であるような錯覚を与える。内部からも透明なガラスごしに広場の活動が窺え、さらにパリの街全体と呼応しているような感覚を与える。この空間を体験する者にとっては意識から建築という実体は消え去り、人々の活動そのものに直接的に反応することになる。この建築は意図されたように、それまでの美術館や博物館などの公的建築が属性としてもっていた権威や力の表現を感じることはない。それは、出来るだけ内部の使用が自由になるように作られた空間構成、その空間構成を利用者にわかりやすくするための導線の明示、空間の成り立ちをわかりやすくみせるように露出させた構造システム、同様にその空間の環境を支える仕掛けが明示される露出した設備システムなどの建築的操作と、どこにでもある、そして誰にでもわかる安価な素材や部品によって組み立てられているためである。
現実の社会は厳然として力の構図が支配し、建築はその力の構図を表象する装置として機能する。建築とは否応なく形態を付随するため、その形態は容易に何らかの表象言語として用いられる。ポンピドー・センターではこの表象が付着するのを拒むように、あらゆる構成要素を露出する。建築の成り立ちを正直にみせることによって形態言語による特定のメッセージが生まれるのを消去しようとする。その結果、建築が従来持っていた言語性は剥奪され、まるで工場や倉庫のように機能を担保するだけの道具のようにみえてくる。しかし、ここで重要なのは工場や倉庫が経済活動のなかでの合目的的道具であるのに対し、ポンピドー・センターでは人間の自由であったり、公平な社会といった精神世界を支えるための道具として提出されていることである。ここで表象言語を拒否するための露出という作法が、反転して新たな表象言語となるというトートロジーに気付く。しかし、この言語性は直接的言語ではなく、最初その露出された構成要素から工場や倉庫にみえるものが、その空間を利用する様態によって再読され、その背後にあるメッセージが読みとれるというものである。建築とは社会的存在であるため時間の経緯のなかで、さらに再読の再読という行為がおこなわれる。開館から20年たったポンピドー・センターはリニューアルのために1997年10月閉館し、1999年12月31日に再び開館した。基本的なコンセプトは保持されているのだが、リニューアルされる前は前面の広場から自由に乗れた透明チューブのエスカレーターは美術館のチケットを買わないと乗れなくなり、広場との連続性が絶たれたようである。内部の商業施設は強化され、最上階の大衆むけのセルフサービスレストランは高級な星付きのレストランに変わった。1977年に開館した当時、暴力的にも見えた露出された構成要素による建築的表現はすでに認知され、誰にでも開かれた大衆にむけたポップ・カルチャーとしての建築は、しだいにハイ・カルチャーの施設としての位置を獲得しつつある。 ポンピドー・センターでみてきたように、建築における「露出」という作法はモダニズム以降の建築の運動に密接に関係している。かつての建築が権力や力を表現する装置として存在していたのに対し、20世紀の建築は社会活動そのものを支える道具として捉えられてきた。そこでは、使いやすく機能的でわかりやすいことが要求される。建築の形態そのものが機能を明示するものであったり、このポンピドー・センターのように建築の組立までも正直に露出するという表現までもとられることとなる。それは自由で公正な市民社会を表現するものとしての「露出」である。現実の社会が不明瞭であり、隠蔽された部分が厳然としてあるからこそ、開かれた公平なヴィジョンとしての建築的表現が要求されているとも言える。(2002.09)
―「建築の終わり」TOTO出版―