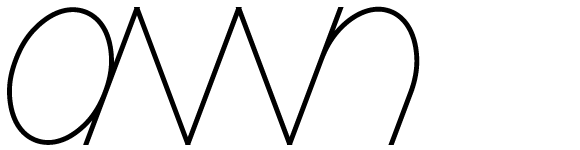
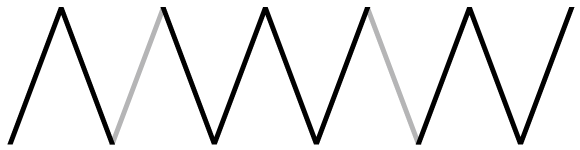
一九七〇年代から八〇年代、日本では若手建築家による建築的冒険がふつふつと湧き出ていた。それは、西欧文明から発したモダニズム運動への抵抗のようであり、同時に、世界を均質に覆い尽くす文化動向に対する地域的な批評行為でもあった。そしてそれは、日本という西欧から見る辺境で起きた新しい建築の「種の爆発」のようにみえた。
ケネス・フランプトンは、このような地域からの文化的批判行為を「ポストモダニズム」や「コンテクスチュアリズム」と関連付けながら、「批判的地域主義」という言葉で表現し、西欧文明の大きな流れのなかの副流として収容した。けれども、今という場からみると、それは副流ではなく西欧文明というレジーム(体制)が解体する予兆をみせていたように思える。西欧文明が生み出した「アーキテクチャー」が相対化され、新しい概念が登場しつつあるようにも思えるのだ。槇文彦氏は、そのモダニズム以降の時代感覚を「漂うモダニズム」という論考で観測している。
今回のレクチャーシリーズでは、独自の建築動向をみせていた日本の七〇年代の冒険を再録し、そこからあらためて未来を展望することを狙った。ギャラリーIHAの主宰者であり、自身も七〇年代の冒険者である長谷川逸子の意向もあって、現在三〇歳代前半の若い世建築家とのクロスダイアローグとし、タイトルは「七〇年代の建築的冒険者と現代の遺伝子」とした。結果として、七〇年代から継続する、ヨーロッパ文明に閉じた批判的地域主義をさらに乗り越える概念が示されたように感じている。本書のはじめに、七〇年前後から今日に至る建築界のクロニクルを記しておきたいと思う。
槇文彦による「漂うモダニズム」では、一九七〇年頃までの建築は、誰もが同じ大きな船に乗っていたが、七〇年代を境にその船から大海原に投げ出され、一人ひとりがバラバラに泳ぎ始めなくてはならなくなったというイメージが提出されている。そのきっかけをつくるのが一九六八年のパリの五月革命だ。それは学生を中心とした既成制度への異議申し立てであり、アメリカを頂点とする資本主義社会への抵抗運動であった。
この時代、日本は産業が急激に拡張して世界で最も洗練された工業技術をもつ国となり、一九六八年には、国民総生産(GNP)がアメリカに次ぐ世界第二位の経済大国となった。そして、敗戦後に制度的に移入された近代的政治である民主主義や近代的生活様式が定着しつつあった。そこでは、建築以外の、演劇、音楽、アート、デザインなどの分野でも寺山修二、荒川修作、倉俣史朗、三宅一生、武満徹、横尾忠則といった文化的リーダーが登場した。同時に、彼らの活動を共有し批評を行なう吉本隆明、多木浩二ら、思想家や評論家も現れ、多様なメディアがその状況を社会に活発に伝えていた。新しい世界の姿は多種多様な活動が同調し、互いに影響し合いながらかたちづくられていく。この時代、近代システムや資本が巨大化して社会を抑圧し始めた状況のなかで、まるで宙吊りにされた解放区のように文化的空間が出現していたのかもしれない。
磯崎新の「建築の解体」は、一九六九年から『美術手帳』で連載が始まった。それは、当時の革命的言説と連動するように、それまでの日本の建築界の主導者たちに幕を降ろし、主役が入れ替わることを示しているように思えた。また、一九六八年に創刊された『都市住宅』は、古い枠組みを乗り越える建築世界を伝えるメディアであり、若い世代はこの雑誌を通して新しい建築の動向を吸収していた。この表紙の企画を磯崎新が担当していて、まるで建築的マニフェストを宣言するポスターのようでもあった。そして一九七〇年に、この革命劇の大団円のように大阪万博が開催される。おそらく一九六八年から七〇年にいたる時期は、新旧の時代が入れ替わる臨界点であったように思える。
一九七〇年代の日本は、経済的に緩やかな成長基調を保ち、豊かな時代を迎えていた。それまでは国家や特権階級しか許されなかった「建物を造る」という行為に一般市民も参加できる社会が実現した。それは第一次世界大戦後、モダニズムの黎明期のヨーロッパで豊かな市民階層が登場し、コルビュジエが彼らをクライアントとして実験的な建築を生み出していたのに似て、一般市民がさほど実績のない若い建築家に住宅設計を依頼するという環境が整い始めていた。この若い建築家たちこそ、本レクチャーの主役である「平和な時代の野武士達」なのだが、この背景には一九六八から七〇年に至る時代の切断を経て、建築的冒険を支える社会の存在があり、新しい建築を受け入れる新しいクライアントが存在したからである。建築は、社会を管理する側ではなく、高い文化意識をもった市民の社会的表現としてつくられるようになり、さらに豊かな経済環境と多様な文化的背景のなかで先鋭化が加速する。
一方、高度経済成長は急激な都市化を推し進め、都市部では土地が細分化されて敷地規模が小さくなりながらも、戸建て住宅が建てられる。この建築状況は、急激な経済拡張と都市膨張という社会環境の大きな変化のなかで生まれている。第二次世界大戦後、西欧世界も同様の社会状況が観測され、その状況に反応してさまざまな都市論が提出され、都市の構成単位である建築のあり方に影響を与えていた。それは、結果的に、都市の変容に向けて提出された建築のアポリアに対する回答を用意することになる。
槇文彦による「平和な時代の野武士たち」という論考は、まさに日本におけるこの建築状況を描写するものだった。
考えてみるとこの数年、外国からやってくる新しい建築の波は必ずしもポストモダニズムだけを標榜しているものではない。たとえば、ロッシ、クリエ兄弟たちのラショナリズムの運動も、レム・コールハースの最新書『Delirious New York』におけるマンハッタン島論、ヴェンチューリの『ラスヴェガスの教訓』、ヴェネヴォロの『近代建築の歴史』、コーリン・ロウの『コラージュ・シティ』アンダーソンの『街路について』、タフーリの『建築とユートピア』など、最近重要だと思われる図書は、ほとんどはすべて本質的には都市論ではなかったか。彼らは都市の文化を論じ、そこから建築の意味を探ろうとしている。米国のアイゼンマンの主宰するIAUS(都市建築問題研究所)の発行する雑誌『Opposition』も、英国の『AD』誌も最近の内容の半分以上はなんらかのかたちで都市の問題とかかわりあっている。(新建築、1979/10)。
この考察のなかで、本来は近代建築運動の本質は都市論であったにもかかわらず、日本ではオブジェクトとしての〈工学的建築〉を主題にしたために都市がおきざりにされていると、この日本における建築の状況を指摘している。
一九八九年、ベルリンの壁が崩壊する。それはソビエト連邦を中心とする共産主義社会の退潮を示していた。そして、一九九一年にソビエト連邦が崩壊し、世界はアメリカ一国による覇権体制となる。資本主義に対抗する原理が不在となり、アメリカの巨大資本が主導するグローバリズム経済という資本の暴走が始まる。
日本ではこの間、一九八九年から一九九一年に、バブル崩壊という経済クラッシュを経験する。この経済状況とリンクして、表現としてのポストモダニズムは終焉する。そして、金融資本主義の独占が始まり、建築はこの透明な経済原理を表出する手段となっていく。
一九七九年にレム・コールハースが『錯乱のニューヨーク』を著して以降、同氏の『S,M,L,XL』以外、都市に関する重要な理論書は出ていない。建築における都市論はこの四半世紀空白である。それは、経済活動のためにつくられた「現代都市」の構造をさらに加速させ、金融資本を中心とする世界が求めるアイコニックオブジェとしての建築が主役の座を占めることになっていたからである。
一九九一年から四半世紀後、二〇〇八年の資本主義システムの世界的クラッシュ、日本では二〇一一年「三・一一」を経験して、人間の共同性や生活を主体とする都市や建築に目が向けられるようになっている。気付くと、一九七〇年前後の時代とは異なる社会状況、それは人口が減少し、経済活動は停滞し、都市は縮減するという状況が目の前にある。都市の膨張期に「七〇年代の建築的冒険」が行われたのは、大きな社会状況の変異に対応するものであった。現代は、七〇年代とは非対称の都市の大きな変化の時代を迎えている。建築は都市によって定義されるとするならば、都市が大きく変化するとき、都市の行く末を知るために都市論が必要とされ、それに呼応して新しい建築が登場するのだ。
一九七〇年代に提出されていた文明論的な世界の危機、そのひとつは、地球環境の有限性であるが、それは人間と物との関係を自然のなかに包摂する概念として再度検討されている。さらに、ヨーロッパ文明を中心とするものではない地域自律型の思想は、世界の多様性を認めるものとして継承され、そして、人間の営みを中心とする思想、それは、槇文彦から示された「共感のヒューマニズム」なのだが、それは依然として私たちの主題であることが確認される。そしてなによりも、巨大化した経済が主導する都市の急激な変化に介入する術を手に入れられないまま、オブジェクトとしての建築に終始してしまった建築状況を批判的に止揚する態度が生まれ始めている。
この連続レクチャーを通して、様々なレイヤーで七〇年代から継続する都市や建築の問題群が浮きあがり、それを貫くようにして回答を求める次の世代の胎動が感じられたと思う。本文を読んでいただきたい。
『建築的冒険者の遺伝子』より