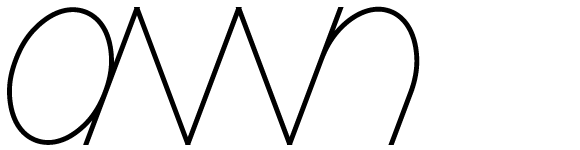
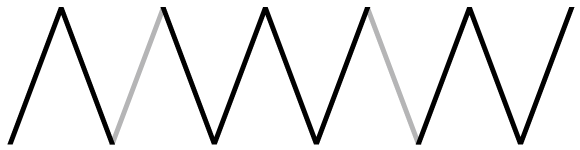
この「建築の公共性」を巡る議論は山本理顕さんの発意によって始まっている。趣旨説明のなかで「ど(・)の(・)よ(・)う(・)な(・)建築であったとしても、その建築は発注者のための単なる私的建築ではない。その建築は同時に周辺の人たちからも共感されなくてはならない」と書かれている。それはあらゆる建築は公共性をもつということを意味している。そして、シンポジウムの冒頭で「建築は人間の生命スパンを超えて存在する。遠い過去から未来にかけて建築は存在し、人々はその空間を体験できる。建築とは私たちの生きる世界を構成するのであるから、建築をつくるということ(空間化)は公共性を現す行為なのだ」と話された。
山本さんの著書『権力の空間/空間の権力』のなかで、ハンナ・アーレントのあるパラグラフが紹介され論が展開されるのだが、私はそのなかで「法とは、境界線である」という一文から、都市のなかはプライベート(私有地)に切り分けられ、その私有地が占有する空間に切り取られた残地は、誰のものでもない、または誰でもが侵入可能な空間となる。この外部空間が公的領域なのだ、と理解した。私的領域と公的領域は相対的であり、あらゆる建築は「外面の現れ」=公共性をもつ。さらに、この公的領域のなかで特定の機能が与えられない共有の空間がコモンズであり、政治的機能が与えられる空間がパブリックとなる。
シンポジウムの後段、大野秀敏さんの発言は重要である。新国立競技場の問題から、「その核心は利権団体がつくったイベントビジネスのために肥大化したプログラムである。それは、イベント興行のための音楽ホールのようなスペックであり、余剰の付帯設備を要求していた。それを税金で作らせようという発注者の意図がある。都市のなかでプライベートセクターを制御するはずの官僚組織は、新自由主義の社会システムのなかで弱体化しており、都市空間の公正なマネージメントする能力を有していない」という報告である。さらに、都市部の公共空間資源が切り売りされて商品化されているという指摘があった。
問題の所在は公共性を失陥させる過大なプライベートにある。私的欲望を統御する公的機能は不全となっている。「建築が誰のためにつくられるのか」、と同時に、「都市は誰のためにあるのか」不明である。都市はそこに住む住人が主人公であるはずなのだが、実態は都市をビジネスの場とする投資家という個人のためにあるようにみえる。巨大再開発で利益を確保するための保留床を政治的につくり、限られた土地に売り床を最大化させるために容積率が緩和される。マーケットメカニズムに都市の行く末を任してしまうために、誰も目的地を知らない「乗り物」になっている。都市の未来ビジョンは誰も示していない。資本主義の終焉が指摘されてはいるが、私たちはまだしばらく資本主義という枠組みから逃れることはできない。革命は未だ起こらない。
建築の公共性を担保するために発注者を個人から集団に代えるという議論がある。法学の領域で使われる「会議体」が参照されるが、それは意思決定システムとして有効であろうか。エリアマネージメントの連絡協議会といっても、利権団体や開発事業者相互の利権調整を行うだけで、そこには、都市の住人や都市空間の利用者は登場しない。そこで、発注者を資本や政治権力から反転させる方法として、大野秀敏さんが『コミュニティによる地区経営』という本のなかで紹介するCMA(Community Management Association:地域経営組合)というアイデアに注目したい。さらに、山本理顕さんは「Local Republic」(自治権をもつ地域社会)という概念を提示している。これも発注の矢印を反転させる可能性を持つ。
シンポジウムで法学者の五十嵐敬喜さんが指摘したように、日本では、2010年あたりに人口のピークを打ち、急激な縮減が始まっている。この人口が減少する社会に対応する都市や建築の理論を私たちは持っていない。近代化という運動に伴う拡張拡大に対応したものではなく、人口が縮減する定常型社会を支える都市や建築の論理が必要になっているのだ。という意味で革命はすでに始まっている。
山本理顕さん、大野秀敏さんのカッコに入れた発言は北山の要約なので、文責は北山にあります。